2022年9月15日-2 花粉情報
未明は曇りでしたが明け方には晴れ、その後も晴れたり曇ったりが続き、気温も明け方は23.0℃しかありませんでした。日中は上昇して午前10時には24.5℃、正午には26.0℃になりましたが、その後も雨は降りませんでしたが天気は不安定でした。

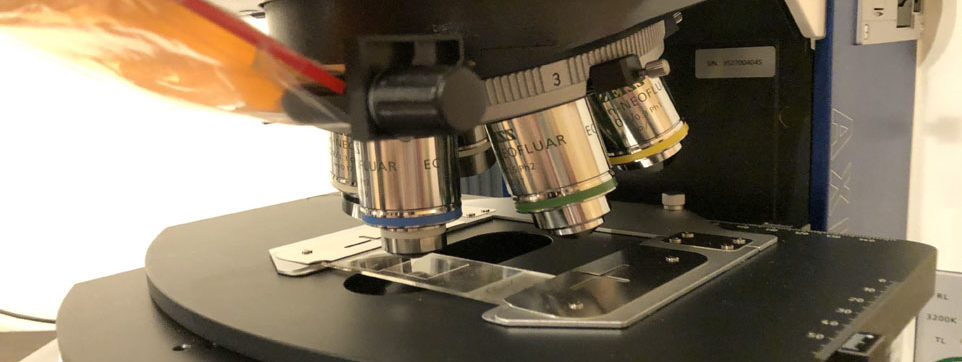
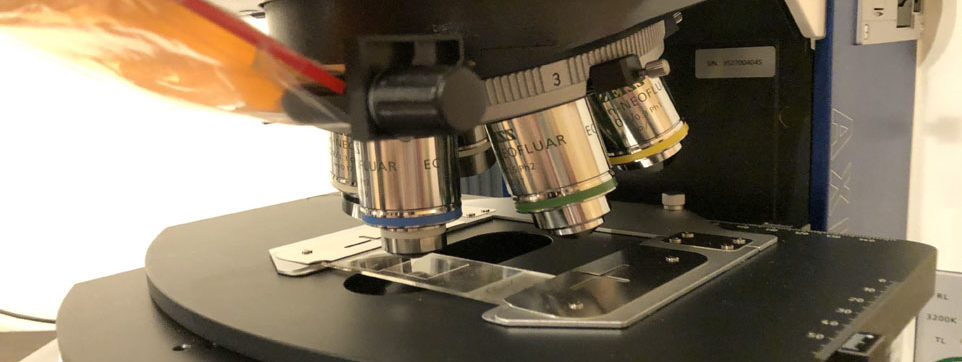
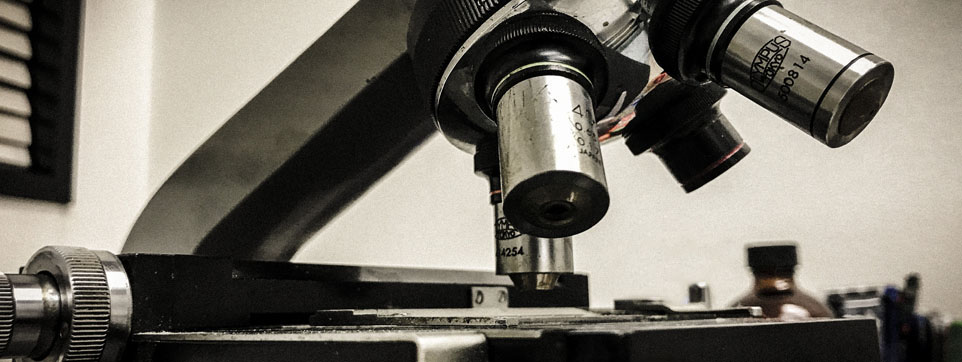


未明は曇りでしたが明け方には晴れ、その後も晴れたり曇ったりが続き、気温も明け方は23.0℃しかありませんでした。日中は上昇して午前10時には24.5℃、正午には26.0℃になりましたが、その後も雨は降りませんでしたが天気は不安定でした。
今年9月上旬の平均気温は25.6℃、日照時間は34.9時間、雨量は45.5mmを記録しました。昨年9月上旬(平均気温は20.7℃、日照時間は13.6時間、雨量は85.5mm)と比較しますと、差は極めて大きく、昨年は10月下旬から10月上旬とほぼ同じでした(気象庁過去の気象データ検索:東京から)。そこで、今年は
1.天気の変化は少なからず人の健康、とりわけ鼻のコンディションに影響を及ぼします。急激な気圧の変動は、鼻 の通気に影響します。体感温度が急に変わると鼻汁分泌過多や通気障害が起こります。これらは知覚、自律神経機能に関係しますが、乾燥冷気は粘膜の機能低下や組織破壊をもたらし、鼻粘膜の様々な障害の原因になります。鼻血が出やすくなるのもこの時期です。従って、寝室の温度と湿度の管理が大事です。
2.この天気は花粉もさることながら室内塵アレルギー(とりわけダニアレルギー)に対しても対策を始める必要があります。室内塵アレルギーは衣替え、転居、大掃除などを契機に悪化します。室内塵アレルギーの主な原因であるダニは、繁殖力が旺盛で数ヶ月で数万から数十万匹に増殖します。抗原となるのは主に糞、抜け毛、フケですが、これらを掃除で完全に排除するのは至難の技です。ダニは畳、絨毯、布団などの内部に生息しますので、これを退治するのも至難です。ダニを増やさない方策が必要です。繁殖前に餌を断つことが大事です。早い時期に餌を断つ掃除を心がけて下さい。また、衣替えをする際は吸入防止のためマスクを着用してください。
今後、この2点の注意が必要と思われます。
未明から明け方までは晴れ、その後も晴れが続き、気温も明け方は25.0℃しかありませんでしたが、日中は上昇して午前11時には30.5℃になりました。暑さは夕方まで続き、夕方は急激に気温が下がりました(午後9時:23.7℃)。
一昨年のこの日、私は某TV局のニュースで、「今秋のインフルエンザは極めて少ない。その理由は、マスク、うがい、ソーシャルディスタンスなどのコロナ対策が効果を発揮した」というニュースを耳にしました。医療現場でそれを実感していました。同時にこれらの対策は極めて有効な花粉症対策でもあります。冬季にインフルエンザに罹患しないこと、冬季の乾燥冷気から鼻粘膜を守ることなどは、花粉症の初期療法の最初に行うべき基本的な対策です。さらに免疫力を高めるための対策ができれば万全とも考えました。
結果は見事でした。インフルエンザはほとんど流行せず、0に等しい結果でした(東京都感染症情報センター:感染症発生動向調査より)。同時にスギ花粉症も飛散花粉数が例年に近いにも関わらず、軽症の方が大半でした。これは、前述の対策が花粉症にも極めて有効で、対策上大切なことであることの証でした。一方今年はほとんどの方がインフルエンザに対する抗体、すなわち免疫がないということになります。この冬は、花粉症の方はインフルエンザの予防上ワクチン摂取を是非とも受けて頂きたいと思います。
未明から明け方までは晴れたり曇ったり、その後も変わりやすい天気が続き、気温も明け方は23.0℃しかありませんでした。日中は上昇して午前9時には27.0℃を超えました。午後も変わりやすい天気で、午後1時と3時には29.5℃まで上がりました。
鼻のアレルギー疾患(アレルギー性鼻炎、花粉症など)は、文字通りアレルギーに起因する病気です。とはいえ、患者の皆様の症状はアレルギーのみによって起こされているとは限りません。アレルギー症状を修飾する因子、増悪させる因子は数多く、併発症や合併症の存在はアレルギー症状をさらに複雑なものへと変貌させます。しかも、診察に際して、患者様は合併症の症状しか訴えないこともしばしばです。例えば、アレルギー性鼻炎が原因で耳管機能が障害されたとすると、受診時に「耳閉感(耳が塞がる感じ)」あるいは「音が二重に聞こえる」など、耳のことしか訴えないこともしばしば見られます。このような場合、原因であるアレルギー性鼻炎を見出して治さなければ、解決には至りません。アレルギー症状を修飾、増悪させる因子の一つに気象状況の変化とりわけ気温の変化があります。今がその時、ご注意ください。
未明から明け方まで晴れ、朝から曇り、その後は曇りが続き、気温も明け方は24.0℃しかありませんでしたが、日中は上昇して午前9時には27.0℃を超えました。午後は晴れが続き、気温は午後1時に30.5℃に達しました。
本日、佐橋 紀男先生から最新の情報をいただきました。
1.2023年春のスギ・ヒノキ花粉飛散予測セミナー(主催:NPO花粉情報協会:理事長 今井 透)
日時 : 2022年9月28日(水曜日) 開演 15:00~16:30
場 所 : 東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニ ガーデンコート1F
紀尾井フォーラム http://kioi-forum.com
講 演 : 「神奈川県における花粉症対策 ―ここまで進んだ花粉対策品種―」
齋藤 央嗣 NPO花粉情報協会副理事長
神奈川県自然環境保全センター 主任研究員
「2023年春の花粉飛散予測」
村山 貢司 NPO花粉情報協会理事 / 気象予報士
◎申し込みは9月5日よりFAX、メールにて受け付けます。申込書は協会HPにあります。
締切日9月25日 FAX:050-3730-9540 e-mail : npokafun@aol.com
◎受講料: 22,000円 (9月26日までにお振込み下さい)
振込み先 三井住友銀行 習志野支店 普通口座 4154963 NPO花粉情報協会
2.NPO花粉情報協会事務局(習志野市)でも秋の花粉調査を再会します。
3.村山氏の話では東日本は軒並み1万を越える地点が多いが、西日本は1万を超える地点はないようです。
最近3年について、気象の影響の有無を確認するために、以下の比較(測定前1週間の気象)をしてみました。
| 年度 | 平均気温 | 雨量 | 日照時間 | 総花粉数 |
| 令和2年 |
27.2 |
59.5 | 35.0 | 6.8 |
|
令和3年 |
22.2 | 23.0 | 14.5 |
19.1 |
| 令和4年 |
25.6 |
7.5 | 27.0 |
14.5 |
総落下花粉数は気温や日照時間の影響を受け、雨量との関係はなさそうな結果でした。今後も検討してみたいと思います。
9月以後に観測される花粉総数は過去2年ほぼ同じ傾向が認められました。
9〜10月の観測総数(個/cm2/週):
| 時期 | 8/30〜 | 9/6〜 | 9/13〜 | 9/20〜 | 9/27〜 | |
| 観測数 | 2020 | 6.1 | 6.8 | 14.6 | 36.6 | 28.2 |
| 2021 | 11.7 | 19.1 | 26.1 | 27.1 | 19.4 | |
| 2022 | 2.1 | 14.5 | ||||
春と比較しますと秋は落下花粉が少ないことが解ります。秋の花粉にも勿論飛散期があって、イネ科はピークが2峰あり5〜6月と10月中旬〜11月中旬、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラのピークは1峰のみで飛散期間も比較的短く、スギのように長期に及ぶことはなく、ブタクサ、ヨモギのピークは9月中旬、カナムグラは9月下旬から10月上旬にピークを記録することが多い傾向にあるようです(東京都福祉保健局の花粉情報(東京アレルギー情報nabi)の千代田の測定値から)。当地でも昨年、一昨年と同じような傾向が見られました。
未明から明け方まで晴れ、朝から曇り、その後は曇りが続き、気温も明け方は22.5℃しかありませんでしたが、日中は上昇して午前9時には27.0℃を超えました。午後は晴れたり、曇ったりの天気で、気温は午後2〜4時に27.5℃に達しました。
昨年のこの1週間(9/6〜9/12)の観測花粉は、「スギ花粉は0.0個/cm2/週、ヒノキ花粉も0.0個/cm2/週、イネ科0.0個/cm2/週、ブタクサ属12.3個/cm2/週、ヨモギ属0.0個/cm2/週、カナムグラ0.9個/cm2/週、マツ0.0個/cm2/週でした。その他の花粉は5.9個/cm2/週でした。その他の花粉にはタデ科花粉が1.9個/cm2/週含まれているようです。花粉総数は計19.1個/cm2/週でした。」と報告致しました。
| 種別 | 観測期間 | |
| 9/5〜9/11 | 昨年(9/6〜9/12) | |
| スギ | 0.0 | 0.0 |
| ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
| イネ科(カモガヤ他) | 0.0 | 0.0 |
| ブタクサ属 | 10.8 | 12.3 |
| ヨモギ属 | 0.0 | 0.0 |
| カナムグラ | 0.6 | 0.9 |
| マツ | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 3.1 | 5.9 |
| 合計 | 14.5 | 19.1 |
今週(9/5〜9/11)観測された花粉は、スギ花粉0.0個/cm2/週、ヒノキ花粉0.0個/cm2/週、イネ科0.0/cm2/週、ブタクサ属10.8個/cm2/週、ヨモギ属0.0個/cm2/週、カナムグラ0.6個/cm2/週、マツ0.0個/cm2/週でした。その他の花粉は3.1個/cm2/週でした。ブタクサ花粉の飛散が目立ち始めました。近隣にブタクサが生えている可能性のある方はご注意ください。
未明まで曇り、明け方のうちに晴れ、その後は晴れが続き、気温も明け方は23.5℃しかありませんでしたが、日中は上昇して午前9時には27.0℃を超えました。昼には29.5℃まで上がり、ほぼ一日晴れ、午後8時過ぎてから曇りました。
そろそろ当地はブタクサ花粉の飛散がピークに迎います。そこで、本日は花粉症の話題に戻します。スギ花粉と比較するとブタクサ花粉は、明らかに小さく、直径はスギの1/3程度しかありません。そのため、スギ花粉よりも鼻を通過する可能性が高く、鼻の症状のほかに咽喉頭の違和感や咳を訴えることが多い傾向があります。当地では飛散期間が短く、飛散数は少ないので、あまり目立たちませんが、秋に鼻アレルギー症状を訴える方がおられたら、考慮すべき原因です。
未明は晴れ一時雨、明け方は晴れ一時曇り、朝は曇り一時雨、昼前は曇り、目まぐるしく天気が変わりました。気温はやや低く(午前2〜5時:22.5℃)、午前中は低いままでした。午後は昼過ぎから曇りが続き、気温も低いままでした。
口腔アレルギー症候群の診断は、「詳しい問診(症状が出る前、15分位の間に食べたもの、花粉症の有無、原因の確認など)、経験の豊富な医師のもとで可能性のある食べ物を極少量口に含んで見る(負荷試験)、皮膚試験(原因となる食物を針で刺し、その針を用いて皮膚試験をする)、あるいは血液検査によって反応する蛋白(抗体)の有無を確認する」などの検査を行い診断します。
治療はまず予防です。アレルギー症状は患者さんに様々な誘因が重なった時に症状がより出やすい傾向があります。OASの患者さんも、風邪をひいていたり、消炎鎮痛薬を服用したり、寝不足、疲れ、ストレスなどがかかった状態や、女性であれば生理の前後などには、これらが誘因となってより症状が出やすくなりますので、特に注意が必要です。その上で抗原の回避(原因物質との接触を避ける)、食物の加熱処理をする、薬物(抗アレルギー剤を服用)により症状を抑える、免疫療法(ブタクサ花粉症であれば、ブタクサの抗原液を用いて免疫療法を行う)などが行われます。
昨日から続いて昼前まで晴れ、昼前から曇り空が広がりました。しかし、気温はやや高い(午前1〜6時:26.0℃)午前中でした。午後は昼過ぎから曇り、夕方は一時小雨が降り、その後は再び曇るという変わりやすい天気でした。
花粉症の皆さんは、ある種の野菜や果物が口腔粘膜に接触すると、その直後から数分以内に口腔、咽頭、口唇粘膜の刺激感、かゆみなどがあらわれることがありませんか。多くの症状は口腔内に限局し自然に消退しますが、時に消化器症状が誘発されることもあります。大豆(特に豆乳)やセロリ、スパイスではアナフィラキシーショックなど重篤な全身症状を呈することがあります。このような反応(果実アレルギー)は抗原となる花粉と野菜や果物に含まれるタンパク(抗原)の共通する(交差抗原性)抗原性に基づいており、まず花粉により感作が成立し、その後、それらの抗原に対して交差反応性を示す抗原を含む果物や野菜を経口摂取した際に主に口腔粘膜において過敏反応が誘発されます。これらを口腔アレルギー症候群と呼びます。
口腔アレルギー症候群を起こす秋の花粉症と食物は、ブタクサ花粉症ではメロン、スイカ、バナナなど、ヨモギ花粉症ではセロリなど、イネ科花粉症ではモモ、トマト、ピーナッツ、メロン、スイカ、ヒマワリなどが報告されています。食べ物のタンパクが原因となる食物アレルギーとは異なります。心当たりのある方は、専門医にご相談下さい。
昨日から続いて昼前まで晴れ、昼前から曇り空が広がりました。しかし、気温はやや高い(午前1〜6時:26.0℃)午前中でした。午後は昼過ぎから曇り、日中は然程気温は上がらず、夕方は小雨が降り続き、夜には再び曇るという変わりやすい天気でした。
9月第2週、例年ですと秋の花粉の飛散がピークを迎える時期です。一昨年、当地でのブタクサのピークは、9/20〜9/26の週の12.8個/cm2/週でした。昨年は第2週(9/6〜12)がピークで12.3個/cm2/週でした。ブタクサ花粉はスギ花粉やヒノキ花粉と比較すると、明らかに小さく、直径はスギの1/3程度しかありません。そのため、スギ花粉よりも鼻を通過する可能性が高く、咽喉頭の違和感や咳を訴えることが多い傾向があります。当地では飛散期間が短く、飛散数が少ないので、あまり目立たちませんが、秋に鼻アレルギー症状を訴える方がおられたら、考慮すべき原因の一つです。
未明は晴れ、明け方に小雨、朝は再び晴れ、気温はやや低い(午前1〜6時:25.0℃)午前中でした。昼前から気温は急上昇(午前9時:28.1℃)、午前11時には30.0℃まで達しました。その後も晴れて昼前には31.5℃になりました。
9〜10月の観測総数(個/cm2/週):9月以後の観測される花粉総数は過去2年ほぼ同じ傾向が認められました。
| 時期 | 8/30〜 | 9/6〜 | 9/13〜 | 9/20〜 | 9/27〜 | |
| 観
測 数 |
2020 |
6.1 | 6.8 | 14.6 | 36.6 | 28.2 |
|
2021 |
11.7 | 19.1 | 26.1 | 27.1 |
19.4 |
|
| 2022 |
2.1 |
|
||||
春と比較しますと秋は落下花粉が少ないことが解ります。秋の花粉にも勿論飛散期があって、イネ科はピークが2峰あり5〜6月と10月中旬〜11月中旬、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラのピークは1峰のみで飛散期間も比較的短く、スギのように長期に及ぶことはなく、ブタクサ、ヨモギのピークは9月中旬、カナムグラは9月下旬から10月上旬にピークを記録することが多い傾向にあるようです(東京都福祉保健局の花粉情報(東京アレルギー情報nabi)の千代田の測定値から)。昨年、一昨年と当地でも同じような傾向が見られました。
未明は晴れ、明け方一時曇りましたが朝は晴れ、気温はやや低い(午前1〜6時:24.5℃)午前中でした。昼前から気温は急上昇(午前10時:27.6℃)、午後2〜4時には30.0℃まで達しました。夜も晴れが続き、気温はやや高めでした。
花粉観測の第一任者の佐橋 紀男先生から
「昨晩の花粉情報、拝見しました。ブタクサ花粉が昨年よりかなりの減少ですが、関東以外でも8月下旬にまだ殆ど観測されていません.7、8月の天候不順が開花を遅らせている可能性もあると思っています。」
「先週になってしまいますが、自宅周辺のスギを観察してきました。前回よりかなりはっきり雄花が沢山ついているのがわかりました。昨年より明らかに多いようです。」
以上、ブタクサ花粉とスギ花粉について貴重なコメントをいただきました。厚く御礼申し上げます。
飛散花粉数の多少には、「気象の影響が大きいのではないか」と考え、過去3年について比較してみました。
| 年度 | 平均気温 | 雨量 | 日照時間 | 総花粉数 |
| 令和2年 |
27.9 |
21.5 | 37.7 |
6.1 |
| 令和3年 |
28.7 |
79.5 | 12.1 |
11.7 |
| 令和4年 |
24.9 |
36.5 | 19.2 |
2.1 |
最も差が大きいのは気温でした。日照時間や雨量とは、一定の関連はないように見える結果でした。今後も検討してみたいと思います
未明から晴れ、明け方一時曇りのましたが朝は晴れ、気温はやや低い(午前1〜7時:24.0℃)午前中でした。昼前から気温は急上昇(午前10時:28.0℃)、午後2〜3時には30.5℃まで達しました。夜には再び曇り、暑さもおさまりました。
昨年のこの1週間(8/30〜9/5)に観測された花粉は、「スギ花粉は0.0個/cm2/週、ヒノキ花粉も0.0個/cm2/週、イネ科0.6個/cm2/週、ブタクサ属9.6個/cm2/週、ヨモギ属0.0個/cm2/週、カナムグラ0.0個/cm2/週、マツ0.0個/cm2/週でした。その他の花粉は1.5個/cm2/週でした。プレパラートの汚れはこれまでほぼ同じ、花粉はやや増えて、総計11.7個/cm2/週でした。いよいよ秋の花粉シーズンのようです。9月前半はイネ科、ブタクサ、後半はヨモギ、カナムガラのピークを迎える可能性が高いと考えられます。近隣にこれらの草が見られる方はご注意ください。」と昨年は報告しています。
| 種別 | 観測期間 | |
| 8/29〜9/4 | 昨年(8/30〜9/5) | |
| スギ | 0.0 | 0.0 |
| ヒノキ | 0.0 | 0.0 |
| イネ科(カモガヤ他) | 0.3 | 0.6 |
| ブタクサ属 | 0.3 | 9.6 |
| ヨモギ属 | 0.0 | 0.0 |
| カナムグラ | 0.6 | 0.0 |
| マツ | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 0.9 | 1.5 |
| 合計 | 2.1 | 11.7 |
今週(8/29〜9/4)観測された花粉は、スギ花粉0.0個/cm2/週、ヒノキ花粉0.0個/cm2/週、イネ科0.3個/cm2/週、ブタクサ属0.3個/cm2/週、ヨモギ属0.0個/cm2/週、カナムグラ0.6個/cm2/週、マツ0.0個/cm2/週でした。その他の花粉は0.9個/cm2/週、落下花粉の総計は2.1個/cm2/週でした。今年のブタクサ花粉初観測は先週でした。同期のブタクサ花粉の飛散数は、昨年より少なく0.3個/cm2/週でした。ピークが昨年より遅い可能性があります。
未明から晴れたり曇ったりの天気が続き、気温はやや低い(午前1〜6時:23.5℃)午前中でした。朝から晴れましたが、気温は昼過ぎ(午後2〜3時:28.0℃)が最高でした。
この1週間変わりやすい天気が続いています。秋の変わりやすい気候による健康面への影響が出る可能性があります。花粉症やアレルギー性鼻炎のみならず健康な方でも大きな温度差に影響を受けるとアレルギー様症状(鼻水、くしゃみ、鼻づまりなど)や咽喉の違和感が出る可能性があります。当科へ来院される多くの方が症状とりわけ喉の違和感を訴えます。これは温度差、湿度差による場合が大半です。室内の環境および体調には十分御注意下さい。
未明は晴れから小雨、朝は小雨、気温は昨日より低く(午前1〜6時:25.5℃)、昼過ぎから気温が下がり(午後1〜7時:23.5℃)、小雨は夕方まで続きました。夕方から曇るも朔日と比較すると大幅に気温が下がりました。
昨日から急に気温が大きく変わりましたが、寒暖差が大きな時期です。例年当院の患者の皆さんは残暑が続く間は原因抗原に関わらずアレルギー症状が軽い方が多い傾向にあります。その理由は、気候条件にあって、残暑によって高温、高湿の気候であった方が鼻のコンディションが良く保たれ、また暑い日が続く間は秋の花粉の本格的な飛散開始前であり、かつ室内塵の季節も来ていないからと思われます。秋の花粉の季節は9月中旬から、室内塵は衣替えが引き金となりますので当地では10月が本番となります。
とはいえ、本日のように突然気温が変わりますと、花粉症、アレルギー性鼻炎ともに温度差の刺激によってアレルギー様症状が出ることがあります。また、室内塵アレルギーの方は、冷暖房の影響、収納していた寝具や衣類などの出し入れの際に埃をあびて一時的に症状の悪化がもたらされることがありますのでご注意下さい。
当院では、東京都内(品川区 五反田)で顕微鏡下で計測した花粉飛散数、および花粉情報など試験的に提供しています。1984年から観測は開始しており、例年2月〜4月のスギ・ヒノキ花粉数を計測しています。
2026年1月25日 休診日が不定期にあります。ご迷惑をおかけしますが、受診される際には、HPでの診療日の確認あるいはお電話でのお問い合わせでご相談下さい。
2021年10月29日 予約制を導入しました。ご予約は、窓口または電話03-3491-2822(月〜金曜日の午後2 時から午後7 時)でお願いします。
ご予約を優先とさせていただき、より待ち時間の無い診療を心掛けて感染対策をして参りますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。病状に応じて、前後する場合があります。
2024年3月25日 日本経済新聞社に、花粉観測に関して情報提供をさせていただきました。
2024年6月1日 保険医療機関のおける掲示
2024年6月1日 個人情報保護方針の掲示
2018.1.18 東京都花粉症患者実態調査について