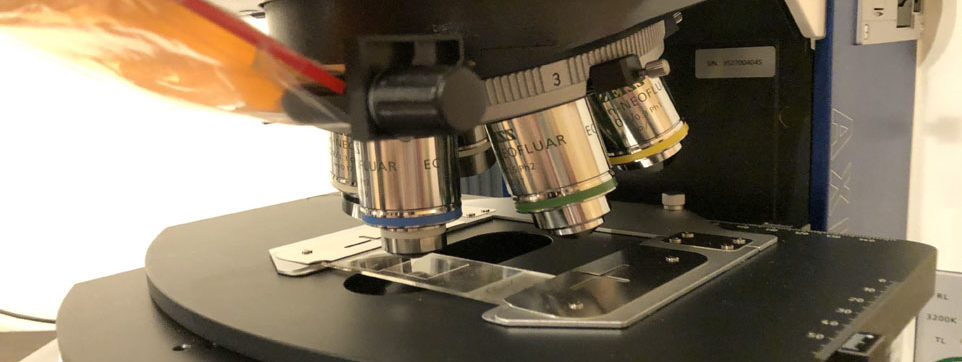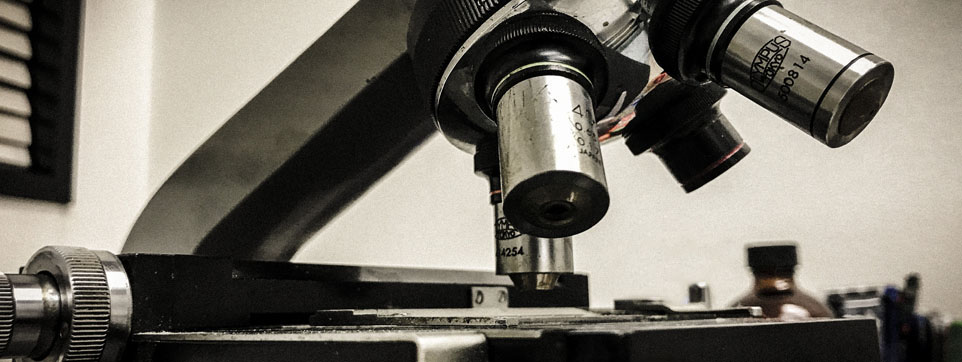令和7年7月31日(木)-1 花粉情報
昨日、当地の落下花粉(ダーラム法による計測)は、総花粉数0.9個/cm2でした
17日から平均気温が27.0℃、最高気温が31.0℃を超える猛暑が続いています。
スギ花粉は、前年夏につくられますが、その量は夏が晴れて暑ければ、暑いほど翌年多く産生され、多数飛散する傾向が認められます。来春は、多くなる可能性があります。現時点では、「スギの新枝の成長も遅れているようです。」と佐橋 紀男先生から情報をいただきました。
とはいえ、暑気あたり、夏バテは後々に影響します。対策を十分講じて下さい。