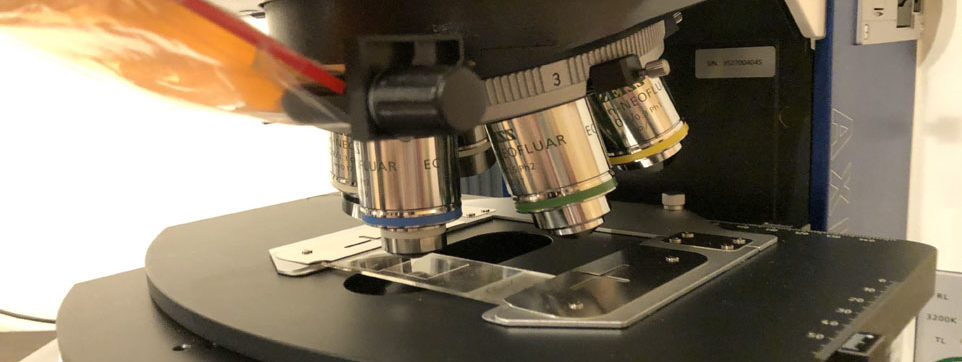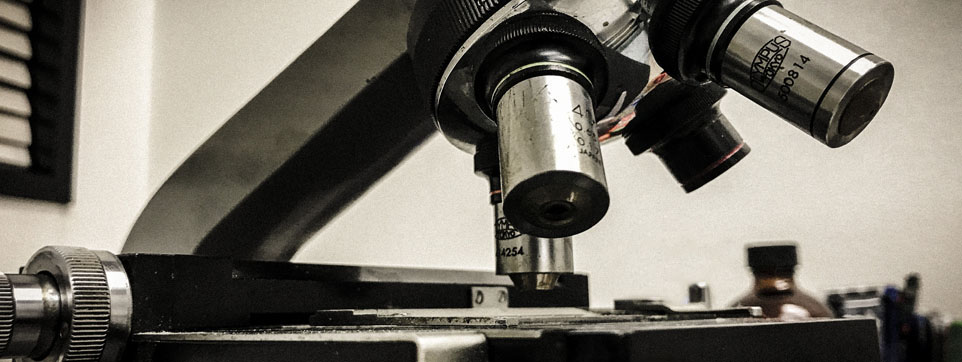2025年05月26日(月)-3 花粉情報
情報はどのように伝えられているか
もっとも花粉飛散情報を必要としているのは、その花粉が抗原の花粉症の方であることに、異論はないと思います。 このことは、アレルギー診療に携わる全ての医療関係者が、理解していると考えます。そのため、少しでも多くの医療関係者や患者様がおられる医療現場に知らせる必要があります。そのため本邦では、以下のようなシステムができています。
- 組織的な情報源
東京都の花粉情報システム:東京都は都衛生局内に設置された「花粉 症対策検討委員会」で疫学調査(患者実態調査)を1983 年から1987年にかけて行った。一方、1984 年から都内保健所 6 カ所で花粉の調査をダーラム型(重力法)で開始し、多摩地区ではスギの雄花の観察を開始した。さらに、1986 年から翌年の花粉飛散数と飛散開 始日の予測を始め、1987年から都民にスギ花粉情報の提供を開始した(東京都衛生局編 1989)。 関東甲信越スギ花粉情報ネットワークとして気象協会が自治体、大学、森林総研、都衛生局、国立病院(相模原病院)などの測定データをまとめて、情報源施設ならびに報道機関(TV、ラジオ、新聞)に、通報されている。
福岡&九州各県花粉情報システム:九州で最初に花粉情報システムを構築したのは福岡市である(長野ら 1987)。 花粉情報が流されたのは 1988 年からである。その後 も国療南福岡病院が中心となり 1990 年には九州全体の 九州花粉速報システムを構築している。 福岡県19ヶ所期優秀各地23ヶ所の測定データを国立療養所南福岡病院に通知、気象協会からの気象情報および花粉症患者受診状況を加味して情報を福岡県医師会の福岡県メディカルセンターを経由してマスコミ、医師会等に伝えられる。
京都府の花粉情報システム:我が国で最初に花粉情報をマスコミを通して発信したのは、1986 年の京都のケースである(水越ら 1987)。このシステムは京都府立医科大学耳鼻咽喉科および関連病院での花粉測定を1982 年から開始。スギ花粉情報センター(済生会京都府病院耳鼻咽喉科)は関連病院から花粉観測数と患者情報を入手し、これをまとめて京都府立医大の耳鼻咽喉科に送り、ここで翌日の花粉数や患者情報を作成し、これらをスギ花粉情報センターにフィードバックして、京都新聞に速報値が送られ、翌日の朝刊紙にスギ花粉情報として掲載された。近畿地方における花粉情報システム:気象協会関西本部内に近畿花粉情報センターをおき、近畿花粉症研究会(各地花粉観測期間)、製薬会社、報道が協力してシステムを構成している。
山形県の花粉情報システム:山形県の花粉情報の草分けは山形市にある県衛生研究所で、1983 年から山形市で花粉飛散調査を開始し、 1987 年には日本気象協会へ調査結果の提供を開始し た。さらに 1991 年には県内 4 地点の調査結果を日本 気象協会へ情報提供し、1998 年には県医師会 HP に花 粉情報を公開(1 週間ごと更新)した。次いで2003 年に県衛生研究所の HP に花粉情報を公開した。 高橋裕一専門研究員らが従来の古典的なダーラム型捕集器を使っ た重力法以外に、欧米では普及しているバーカード型捕集器を使った体積法による調査を開始し、テープ上に経 時的に捕集された花粉を顕微鏡下で数えるのではなく、 酵素免疫学的な方法(イムノブロット法)により花粉を肉眼で視覚化できる方法を開発した(高橋ら、1990)。 このことから、いち早く 2003 年から同研究所 HP に花粉情報に合わせて、わが国で初めてアレルゲン(Cry j 1) の飛散量をグラフで掲載している。
これらのシステムは、1995年当時既にできていました(スギ花粉のすべて:(株)メディカルジャーナル社)。そして高度化が計られて(我が国における花粉情報の高度化:佐橋 紀男:森林化学73 2015.2 P6〜)ました。こうしたシウテムの全国版があると、旅行者や出張を頻繁にする職業の方に大いに役立つとおもいます。